|
捕まえた正樹を引きずるようにして、土蔵に真奈美が入ってきた。
空いている左手に点した炎が薄暗い土蔵の中を照らし出し‥‥‥
壁を睨んだ真奈美の唇が、ゆっくりと、笑う形に吊り上がる。
見極めろ 見極めろ 見極めろ 相手は誰なんだろ? そしてどこにいるのか
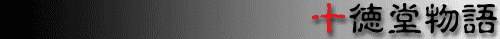
episode.04:「F.E.A.R」
|
|
「‥‥‥ははっ‥‥‥あっははははははははははははっ!」
途方に暮れるチャムナ。
呆気に取られる菜織。
どう反応していいかわからない正樹。
遅れて駆け込み、肩で息をつく乃絵美。
そして、ひとり哄笑する真奈美。乾いた笑い声が何もない土蔵に響き渡る。
十徳神社、土蔵。
「ねえチャムナ、あんたたちって一体どうなってるわけ?」
「マナミについて聞いているのなら、私が教えて欲しいくらいだ」
「あっそ‥‥‥」
呆れたように言いながら、菜織は真奈美に向き直る。
「で、真奈美? どれがレナンなの?」
「ないよ」
「は?」
「ないよ‥‥‥あははははっ‥‥‥あはははははははっ! あーっはっはっはっはっはっはっはっ!」
哄笑は続く。真奈美の動きに合わせて、ゆらゆらと揺らめく炎が壁を不規則に照らす。
「何がそんなにおかしいわけ?」
不審そうに菜織が尋ねる。返答はない。
乃絵美はずっと真奈美の赤いペンダントに目を凝らしていた。真奈美が左手に掲げた、灼けつくような炎の塊がすぐ胸元にある。目が痛い。涙が滲んでくる。それでも、乃絵美はそこから目を離せなかった。
違和感が拭い切れない。どうしてもそれが、深くて透き通るような‥‥‥青い石、だったような気がしてしまう。はっきり憶えているわけでも、前からよく知っているわけでもない。ただ、あの石は本当は青い石で、赤くなった時に砕けたものがあるような、そういう気がするのだ。
砕けたものは何だろう。あの石は、どうして青くないんだろう。
考えたところで乃絵美に理由がわかるわけもない。当たり前のことなのに‥‥‥あの石にとって、それはとても悲しいことなのだと、理由もなく乃絵美は確信していた。涙が零れて止まらないのは、燃え盛る炎をじっと見つめ続けていたから、だけではなかった。
ようやくのことで正樹が真奈美の手を振り切った。
正樹の手を追いかけようとして真奈美の手が宙を泳ぎ‥‥‥不意に、その手は真奈美の胸へ向かっていった。苦しげに胸のあたりを掻き毟りながら、譫言のように何かを呟いている。今は正樹どころではないらしい。
「おのれレナン‥‥‥」
小さな小さな声で呟いた真奈美の言葉を乃絵美は聞き逃さなかった。
そして、同じその一瞬、菜織には正樹のことしか頭になかった。
「正樹っ!」
床に転がった正樹に駆け寄ろうとした菜織の脇腹に、不意に、日焼けした長い脚が襲いかかる。
「ぐう‥‥‥っ‥‥‥」
見事に不意を突かれた菜織は、一撃で駆け寄る前の位置まで叩き返されてしまった。
「お前の相手は私だ」
菜織と正樹の間に立ち塞がるのはもちろんチャムナだ。その瞳はマナミの変容に困惑する内心を隠し切れずにいるが、それでも今は、彼女にはマナミを信じる以外になかった。
「くふっ‥‥‥何すんのよチャムナっ!」
蹴りを喰らってしまった脇腹をさすりながら菜織が立ち上がる。
「あたしたちがいつ、あんたとレナンの邪魔をしたって言うの? そこの真奈美がレナンはいないって言ってるのに、こんなんでケンカしたらからって何がどうなるってのよ! ここにそのレナンがいるってんならさっさと持って行けばいいじゃない! どうなのよチャムナっ!」
「うるさいっ! うるさいうるさいうるさいっ!」
ナオリを仕留めて‥‥‥だから、どうなるというのか。マナミは何をしようとしているのか。わからない。何もわからない。
チャムナは迷っていた。その迷いを振り切ろうとでもするかのように、闇雲に菜織に食ってかかる。
「チャムナさん違う‥‥‥違うよ! やめて! もうやめてっ!」
菜織を庇うように、乃絵美が菜織の前に出た。その顔のすぐ脇を蹴り足が吹き抜ける。菜織が乃絵美を突き飛ばす。間一髪で乃絵美への直撃は免れたが、代わりに菜織がその足に突っ込んでいく形になってしまった。
「くうっ‥‥‥」
「菜織ちゃんっ!」
チャムナが止まらない。明らかに苛立っているが、かといって、デタラメな攻めかといえばそうでもない。生来のセンスなのか、生半可な鍛え方ではなかったのか、あるいは両方当たっているのか。理由はわからないが、とにかく菜織には手がつけられない。
このままじゃ勝てないかも知れない。これ以上やられたら‥‥‥怪我させないように、なんてもう言ってられなくなるかも知れない。防戦一方の菜織は思わず唇を噛み、
「っ!」
瞬間、放たれた足払いにバランスを崩し、仰向けに倒れてしまった。すかさずチャムナが馬乗りにのしかかる。右腕を振り上げる。振り下ろす。
「ごめん!」
いきなり横からチャムナを蹴飛ばした足があった。正樹だ。その「ごめん」は、きっとチャムナに謝ったのだろう。そういう正樹のことが、菜織は嫌いではなかった。
狙いが外れたチャムナの右腕は身体ごと真横に転がっていく。
菜織とチャムナの間に割って入った正樹と、正樹たちと真奈美の間にいるチャムナ。状況は何も変わってはいない。
「お兄ちゃん! 大丈夫? 火傷とかしてない?」
「大丈夫だ。それより乃絵美、何か言いたそうだぞ?」
「え、あの‥‥‥うん。考えてることがあるんだ、だから」
「今急いでるから、要件だけにしてくれる?」
菜織に急かされて、乃絵美は困ったような顔をした。
「んーっと、説明するのにはちょっと時間かかるから‥‥‥無茶なお願いでもいい?」
「‥‥‥あー‥‥‥善処するから、取り敢えず言うだけは言ってみて」
「どっちかを連れて、考え事できる場所に逃げたいなって思ってるの。どっちかっていうのは、チャムナさんか、真奈美ちゃんのペンダント。両方でもいい‥‥‥本当は、両方欲しい」
本当に無茶だった。
「なあ菜織、お前どっちが難しくないと思う?」
「嫌な聞き方ねそれ‥‥‥まあ、強いて言うならチャムナの方が難しくないかな」
「奇遇だな。俺もそう思ったよ」
「それじゃ決まりね? 動いたら一気よ。落ち合う場所は‥‥‥あそこにしましょ」
正樹は頷いた。「あそこ」がどこのことかなんて、聞き返すまでもないことだった。
真奈美はまだ床でのたうちまわっている。何がそんなに苦しいのかはわからないが、首元を掻きむしる両手の指の隙間に、淡い、青い光が滲んでいる。真奈美自身から湧き出すような炎の赤に比べればまるで問題にならないような力のように見えても、多分あれが原因で真奈美は苦しんでいるのだろう。
ぼんやりと頭の中にあったものが、やっと、手の届く場所で形になろうとしている。それがレナンを巡る秘密の核心なのだということを乃絵美は知っていた。
そして結局、そんな風に苦しんでいる真奈美を放っておける正樹たちではなかった。
「菜織ごめん、俺やっぱりペンダントの方が難しくないと思う」
「馬鹿。そんなわけないでしょ? わかってるくせに」
しょうがないわね、とでも言いたそうに、菜織は肩を竦めた。
「止めないから行っておいで。チャムナは私がどうにかする」
「できるか?」
「わかんないわ、正直。でも手加減してる場合じゃないから‥‥‥そういうつもりでやれば何とかなると思うけど」
「わかった、そうする。サンキュ‥‥‥行くぞっ!」
☆
十徳神社、土蔵。
正樹の声が狭い土蔵に響き渡り、その一瞬で攻守が入れ替わった。
「チャぁムぅナああああああああああああああああっ!」
まず、菜織が疾った。どこから取り出したのかよくわからないハリセンを右手に掴んで、猛然とチャムナに襲いかかる。
突然の襲来に虚を衝かれたか、棒立ちになったチャムナの脳天にハリセンが炸裂した。紙垂がばさあっと跳ねる。
「!? くう‥‥‥っ‥‥‥?」
明らかに効いている。というより、人間相手にしては妙に効きすぎている‥‥‥一瞬後に菜織は思い出した。確かチャムナは人間じゃなくて精霊だった。精霊は厳密には霊体の眷族だから、それだったら確かに効く筈だ。
それ以上を考えている余裕は今の菜織にはない。よろめいたチャムナに駆け寄って、背中に護符を1枚貼りつける。それでも構えをとろうとしていたチャムナの動きが、紙1枚貼られただけで凍りついたように止まってしまう。
「乃絵美、ちょっと手伝って!」
「は‥‥‥はいっ!」
そのまま、まったく身動きがとれなくなったチャムナを抱えて、菜織と乃絵美は土蔵を出ていく。
「お兄ちゃん‥‥‥」
乃絵美は心配そうに土蔵の入口を見つめたが、
「あいつなら大丈夫よ」
菜織は振り返らなかった。
「真奈美ちゃん! 大丈夫か真奈美ちゃん!」
「正樹くん‥‥‥苦しい‥‥‥苦しいよ‥‥‥」
真奈美の瞳が正樹を見つめた。どこか儚げで、懐かしい黒い瞳。
首元に引っ掻いたような爪の痕が幾つも浮き上がっている。
「これか? 今取ってやるからな」
「だめ‥‥‥取っちゃだめ‥‥‥それじゃ‥‥‥抑え‥‥‥」
ペンダントにかけた手を、真奈美は必死で押し止める。
「いいから!」
「違うの‥‥‥違うの正樹くん‥‥‥それを取ったらもう抑え‥‥‥火之迦具土‥‥‥」
「ひの、かぐつち?」
聞いたことのない何かの名前に、正樹の手が止まる。
その手を握って‥‥‥信じられないくらい強い力で正樹の手を握って、真奈美は話し続ける。
「あたしの中に、そういうのがいるの‥‥‥このペンダントは、レナンさんと同じ力を持っていて、火之迦具土が暴れると、レナンさんの力が、何とかしてくれるの‥‥‥いっつもこうだから‥‥‥心配‥‥‥しないで‥‥‥」
「いっつもって、こんなことが何度もあったのか?」
「うん、何回かは‥‥‥このペンダントは、本当は、あたしがこんなだから‥‥‥自分でどうにもならないような、こんな火なんか持ってるから、それを抑えるために、あたしが下げてるの‥‥‥あたしの火のこと、チャムナさんは知らなかったんだよ‥‥‥ミャンマーにいた頃は一度しかこんな風になったことないから‥‥‥だからきっと、日本に来てからのあたしを見て、チャムナさんも驚いてる‥‥‥」
言っているうちに、ペンダントに填まっていた赤い宝石が、ゆっくりと色を失っていく。火が消えてしまえば‥‥‥さっきまでの赤は嘘でした、とでも言うかのような、青い宝石がそこに残されている。
「よかった‥‥‥」
その様子を見届けると同時に、真奈美は気を失った。安心したのかも知れなかった。
ボロボロに焼けてしまった倉の中で、正樹はいつまでもその宝石を見つめていた。
☆
戒めを解いた途端にまた暴れ出そうともがき始めたチャムナを、菜織が必死で抑えている。
「チャムナさん落ち着いて。もし私が思ってる通りだったら、レナンさんはここにいるよ。だから、大丈夫だから、今だけは私たちの話を聞いて」
乃絵美の一言で急に大人しくなったチャムナから、菜織が手を離す。埃っぽい床にチャムナはぺたんと座り込んだ。
旧十徳神社。林の中に隠れるように埋もれている小さな社。
こんな建物があるなんて乃絵美は知らなかったが、菜織たち3人にとっては昔からの隠れ家だった場所だ。だから真奈美も場所を憶えている筈で‥‥‥つまり、ここに隠れていても真奈美から隠れたことにはならないのだが、その辺は多分、あっちで正樹が何とかしてくれるだろうと菜織は思った。そう思いたかった。
「ゆっくり、ひとつずつ、答えてください」
必要以上にチャムナを刺激しないように、乃絵美は慎重に言葉を選ぶ。
「まず、真奈美ちゃんの持ってるペンダントは、あれは何ですか?」
「あれは‥‥‥マナミの父親が、マナミに預けた。レナンと同じ力を持っているペンダントで、でもレナンの魂はそこには入っていないと聞いた」
「それが本当かどうかは確かめましたか? あのペンダントを、調べてみたことはありますか?」
「精霊がそれを手に持つことはできないと聞いている。何度か触ろうとしてみたが、確かに、どうしても拒否されてしまう」
「じゃあ、あなたたちはここへ、レナンさんの何を探しに来たんですか?」
「私たちは、レナンの魂を探すためにここへ来た。あのペンダントには力しかないからだ」
「もうひとつ。あの赤い石のペンダントは」
「赤い? ‥‥‥嘘を言うな。あれはどう見たって青い石じゃないか。そんなことよりノエミ、レナンはどこなんだ?」
乃絵美は溜め息をついた。
「精霊さん同士は触れあえない、そういう決まりはありますか?」
「ない。‥‥‥ない筈だ。‥‥‥ない、と思う。あったら悲しい」
「うん。私もね、きっとそんなのないと思うんだ。だからチャムナさん、よく聞いて‥‥‥チャムナさんがペンダントに触れないのは、レナンさんがチャムナさんのこと嫌いだからなんかじゃないよ。たまたま、あれはそういう風になってるペンダントだからだよ」
「え? あの、よくわかんないんだけど‥‥‥乃絵美、それどういうこと?」
「多分ね、あのペンダントは本当はレナンさんなんだと思う。力だけとかそういうのじゃなくて、あれは本当にレナンさんの全部なんじゃないかって思う」
「そんな‥‥‥そんなワケないだろう! それじゃどうして、どうして私はあのペンダントに触れられないんだ? あれがレナンなら‥‥‥レナンは私を‥‥‥きっ‥‥‥嫌いになったのか‥‥‥?」
チャムナがそれだけを言うまでに、数分の時間を要した。
「だから、そうじゃないんだよ。チャムナさんがあれを手にとってゆっくり調べちゃったら、多分チャムナさんを最後まで騙すことはできないから、だからチャムナさんには触れないようになっているんだと思う。だって、チャムナさんはレナンさんの魂を探しに来てる筈なんでしょ? ミャンマーで受け取ったペンダントの中にレナンさんがいるって知ってたら、わざわざここまで来なかったでしょ?」
「それはもちろんだけど‥‥‥そんな‥‥‥それじゃ‥‥‥」
「レナンの魂は、わざわざ探さなくたって最初から手元にある。真奈美のお父さんがそれを知らなかった筈はない。つまり本当は、真奈美のお父さんが日本でチャムナたちにさせたかったことは、チャムナたちが知ってる目的とは全然違う。何か別の目的があって日本に送り込んだけど、でも操る方にとっては、理由はレナンの方が都合がいい‥‥‥」
だったら、問題はそこから先だ、と菜織は思う。
「真奈美のお父さんは、チャムナたちにも何かを隠してる。乃絵美、そういうことなのね?」
ゆっくりと、乃絵美が頷いた。
|